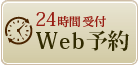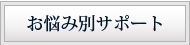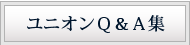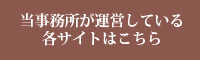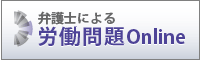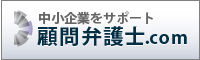解雇が無効になった場合に払う未払賃金には中間収入も含まれますか?
 解雇した従業員が、解雇の有効性を争っている際に別のところで働き始めました。
解雇した従業員が、解雇の有効性を争っている際に別のところで働き始めました。
そこの会社で賃金をもらっているようです。
解雇が無効になった場合、解雇してから他の会社で働いている間の賃金について、弊社からも払わなければならないのでしょうか?


裁判所の判決と労働委員会の救済命令では考え方が異なっています。
裁判所は、平均賃金以上の中間収入については、控除することができると考えています。
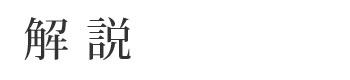
問題点の本質
 Q&A「裁判で解雇が不当労働行為とされた場合、どう対応したらいいですか?」で解説したとおり、解雇が無効とされた場合には、実際に解雇されてから解雇が無効になるまでの期間の賃金の支払義務が会社に生じます。
Q&A「裁判で解雇が不当労働行為とされた場合、どう対応したらいいですか?」で解説したとおり、解雇が無効とされた場合には、実際に解雇されてから解雇が無効になるまでの期間の賃金の支払義務が会社に生じます。
このとき、今回のように無効判決を得るまでの間に、労働者が他の会社で働いて収入を得ていた場合にこの収入をどのように評価するのかという問題が生じます。
解雇がなされなかった場合には他の会社で働くことは想定できなかったのであり、収入を得ることはなかったはずで、それを一切考慮しないのは不合理だという主張が出てくるのは自然なことでしょう。
 法的には、
法的には、
①中間収入は解雇された従業員が償還すべき「債務(労務の提供)を免れたことによって得た」利益(民法536条2項)といえるかどうか
②仮にいえる場合でもこれを使用者が一方的に控除することになる賃金からの控除は賃金全額払いの原則(労基法24条)に反しないか
③解雇期間中の就労不能も休業手当請求権(労基法26条)が発生するが、この請求権が①、②の問題にどのような影響を与えるか
という問題があると整理されます(菅野755)。
【参考裁判例】あけぼのタクシー事件 最一小判昭62.4.2(判時1244号126頁)
 この問題について最高裁判所は、以下のように判断している。
この問題について最高裁判所は、以下のように判断している。
「使用者の責めに帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中の賃金を支払うにあたり右利益(以下、「中間利益」という。)の額を賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち労働基準法12条1項所定の平均賃金の6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である。」
「したがつて、使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち平均賃金額の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきであり、右利益の額が平均賃金額の4割を超える場合には、更に平均賃金算定の基礎に算入されない賃金(労働基準法12条4項所定の賃金)の全額を対象として利益額を控除することは許されるものと解される。そして、右のとおり、賃金から控除し得る中間利益は、その利益の発生した期間が右賃金の支給の対象となる期間と時期的に対応するものであることを要し、ある期間を対象として支給される賃金からそれとは時期的に異なる期間内に得た利益を控除することは許されないものと解すべきである。」
裁判例の検討
 この裁判例からすれば、先ほどの①の論点については、中間収入は債務を免れたことによって得た利益に当たるとして基本的に控除することができると考えていることがわかります。
この裁判例からすれば、先ほどの①の論点については、中間収入は債務を免れたことによって得た利益に当たるとして基本的に控除することができると考えていることがわかります。
しかしながら、③の点で労基法26条の規定により控除ができるのは平均賃金の6割以上の部分だけであると判断しています。逆にいえば、平均賃金の6割までしか中間収入を得ていなければ、使用者は控除が一切できないということになります。
また、②の論点については、使用者による控除を認めているので、賃金全額払いの原則の趣旨に反しないと考えているといえます。
さらに、この裁判例では、毎月の給与だけで控除しきれない中間収入がある場合には、賞与といった労基法で定める平均賃金の対象となっていない部分から控除することができると判断されています。
そして、控除できる中間収入は、実際に解雇されてから解雇が無効と判断されるまでの期間に対応する部分に限られるという点も言及されています。
最高裁判所の判断に対しては、そもそも控除を認めることに反対する見解もありますが(西谷219頁)、これを支持する見解が一般的です(菅野756)。
労働委員会の手続の場合の中間収入控除
 (1)この問題については、労働委員会が不当労働行為の救済命令としてバックペイ(賃金の支払)を認める場合にも裁判所の考え方と同様に考えるべきかという点が議論されてきました。
(1)この問題については、労働委員会が不当労働行為の救済命令としてバックペイ(賃金の支払)を認める場合にも裁判所の考え方と同様に考えるべきかという点が議論されてきました。
(2)この点、労働委員会は長らく中間収入の控除は不要であるという控除不要論の立場に立って、中間収入の控除を行わないという対応を取ってきました。
こうした労働委員会の命令について、行政処分の取消訴訟という形で裁判所に持ち込まれ、判決が出されています。その際、2項で解説した控除を認める裁判所のスタンスとの矛盾をどう考えるかが争点となってきました。
(3)当初の裁判例は、中間収入の控除はしないという労働委員会の命令は、原状回復という救済命令の目的から逸脱するものであるとして裁判所の考えと同じく労働委員会の救済命令の場面でも控除は必要であると判断していました(在日米軍調達部事件(最三小昭37.9.18民集16巻9号1985頁)。
(4)ところがその後、最高裁判所は第二鳩タクシー事件で概要以下のとおり述べて判例変更を行いました(最大判昭52.2.23民集31巻1号93頁)。
すなわち、中間収入控除の要否及びその金額を決定するにあたっては、労働委員会は、解雇によって被解雇者個人が受ける経済的被害の側面と解雇が当該使用者の事業所における組合活動一般に対して与える侵害の面の両面から総合的な考慮を必要とするのであって、そのいずれか一方の考慮を怠り、又は救済の必要性の判断において合理性を欠くときは、裁量権の限界を超え、違法となるとしたのです。
 この最高裁判例からすれば、労働委員会は、裁量の逸脱と評価されない限り、中間収入を控除しないという形で救済を図ることは可能であるということになります。
この最高裁判例からすれば、労働委員会は、裁量の逸脱と評価されない限り、中間収入を控除しないという形で救済を図ることは可能であるということになります。
その意味では、裁判所による司法救済の場合よりも労働委員会の救済命令の方が労働者や労働組合にとって有利な解決になる場合も出てくることになります。
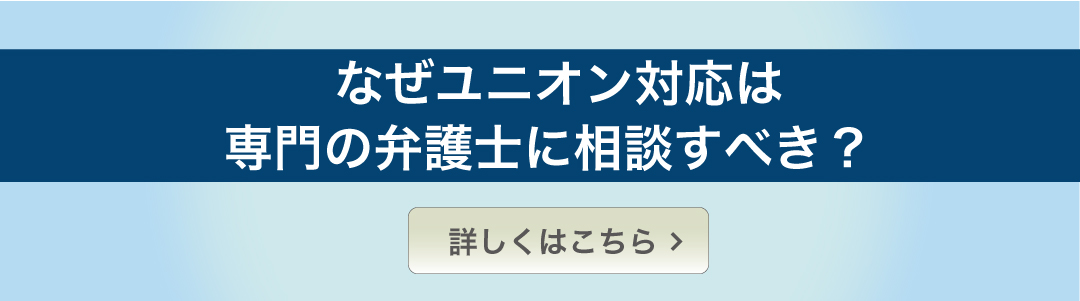
その他の関連Q&A
-
1
ユニオン・合同労組とは? -
2
不当労働行為とは? -
3
労働委員会の手続等 -
4
組合活動の妥当性 -
5
団体交渉への対応方法 -
6
労働協約とは? -
7
争議行為への対応 -
8
紛争の解決制度