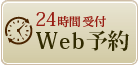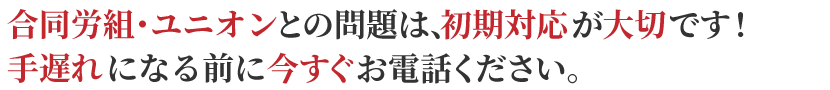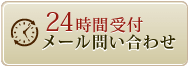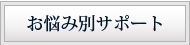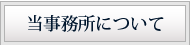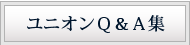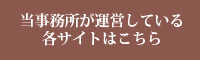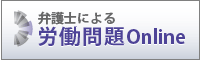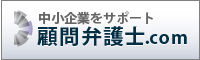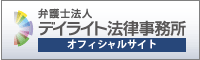裁判所の手続以外に労働紛争を調整できる方法はありますか?
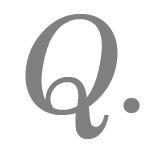 労働組合(ユニオン)との団体交渉が平行線をたどっており、解決できそうにありません。
労働組合(ユニオン)との団体交渉が平行線をたどっており、解決できそうにありません。
裁判所の手続以外に労働紛争を調整できる手続はありませんか?



労働紛争の調整方法として、斡旋、調停、仲裁があります。

労働委員会が行う調整
 労使間の紛争は、話し合いで自主的に解決することが望ましいといえます。
労使間の紛争は、話し合いで自主的に解決することが望ましいといえます。
しかし、話し合いがまとまらないときは、労働委員会が、公正・中立な機関として、 間に入って助力することを「労働争議の調整」といい、労調法にその方法等が規定されています。
労調法は、労働紛争の調整方法として、斡旋、調停、仲裁の3つを予定していますが、実際に申請されるのは斡旋が大部分となっています。
①斡旋(あっせん)
 斡旋とは、労働委員会の会長が指名した斡旋員が、労使間の話し合いをとりもち、あるいは主張をとりなして、争議が解決するように促す方法です。
斡旋とは、労働委員会の会長が指名した斡旋員が、労使間の話し合いをとりもち、あるいは主張をとりなして、争議が解決するように促す方法です。
斡旋の申請ができるのは、労働組合又は使用者です。労働者個人は、この労調法に基づく斡旋は利用できません。
なお、労働者個人については、各自治体独自の紛争処理制度を利用できます。例えば、福岡県では県内4か所の県労働者支援事務所が斡旋を行っています。
斡旋の費用は無料となっています。
斡旋が申請されると、労働委員会会長が、通常、斡旋員候補者名簿の中から公益側・労働者側・使用者側各1人の斡旋員を指名し、3人の斡旋員で一つの事案を担当します。
斡旋員からは労使の間に入って、斡旋案を提示するなどして調整活動を行います。斡旋案とは、問題の解決を図るために、事情聴取を行った結果を踏まえて、斡旋員が労使双方に提示する解決案のことです。この斡旋案を受諾するか否かは当事者の自由であり、強制はできません。
②調停
 調停は、労働委員会の公・労・使の3者の委員で構成される調停委員会が調停案を作成し、その受諾を勧告して紛争を解決する方法です。
調停は、労働委員会の公・労・使の3者の委員で構成される調停委員会が調停案を作成し、その受諾を勧告して紛争を解決する方法です。
進め方は、基本的に斡旋とほぼ同じですが、労使双方からの申請であることや、一方からの申請の場合には労働協約に定めが必要であることなど、斡旋に比べ開始要件に一定の制約が設けられているほか、原則として調停案を示すこととなっています。
ただし、斡旋と同様に調停案は受諾を強制されるものではありません。
③仲裁
 仲裁は、労働委員会の公益委員で構成される仲裁委員会の裁定に、紛争の解決を委ねる方法です。
仲裁は、労働委員会の公益委員で構成される仲裁委員会の裁定に、紛争の解決を委ねる方法です。
申請、進め方は調停に準じますが、斡旋案、調停案に相当する仲裁裁定書が作成されると労働協約と同一の効力を有し、労使双方はその内容に拘束されます。
斡旋の進め方
 斡旋については、具体的な方法が労調法に規定されているわけではありませんが、通常、次の流れで行われています。
斡旋については、具体的な方法が労調法に規定されているわけではありませんが、通常、次の流れで行われています。
①斡旋員が斡旋開始を告げ、労使双方の出席者の確認を行い、その後、申請者、被申請者の順に事情聴取を行って、紛争の争点が何かを確認します。なお、一方の当事者の事情聴取を行っている間、他方の当事者は控室で待機します。
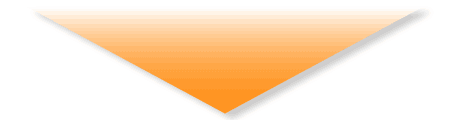
②労使の斡旋員が、労働組合、使用者と個別に面談し、譲り合いを勧めたり、助言を行ったりして両者の主張を調整するとともに、3人の斡旋員が場合によっては解決案として斡旋案を提示して、紛争の解決を図ります。
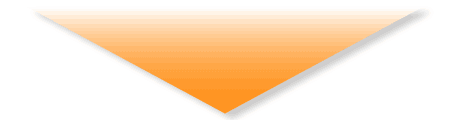
③当事者間の主張に大きな隔たりがあり、斡旋員が解決困難と判断した場合には、その時点で斡旋を打ち切ることもあります。
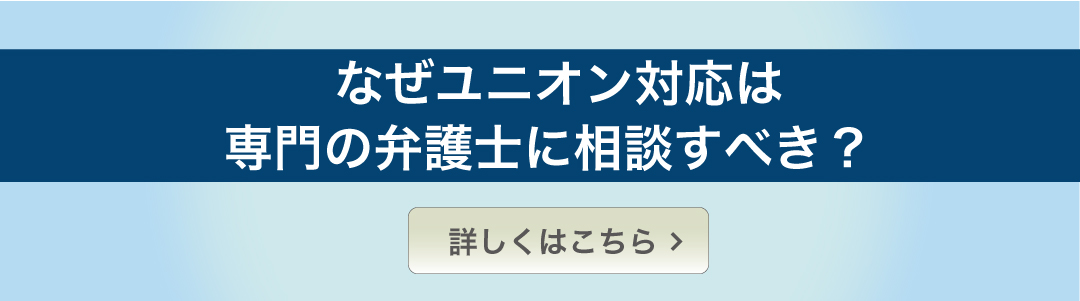
その他の関連Q&A
-
1
ユニオン・合同労組とは? -
2
不当労働行為とは? -
3
労働委員会の手続等 -
4
組合活動の妥当性 -
5
団体交渉への対応方法 -
6
労働協約とは? -
7
争議行為への対応 -
8
紛争の解決制度