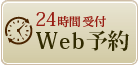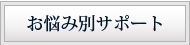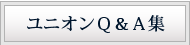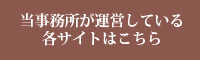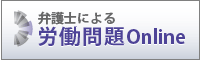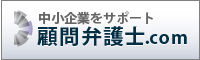すでに解雇した社員でも解雇撤回の団体交渉に応じる義務がありますか?
 解雇した元従業員が、所属するユニオンを通して解雇の撤回を求めてきました。
解雇した元従業員が、所属するユニオンを通して解雇の撤回を求めてきました。
団体交渉に応じる義務はありますか?



被解雇者が解雇の効力を争っている場合、基本的には団体交渉に応じる義務があります。
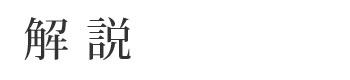
被解雇者が属する労働組合
労組法は、「使用者が雇用する労働者」の代表者と正当な理由なく団体交渉拒否した場合を不当労働行為になると規定しています(労組7条2号)。
この条文の文言を見れば、解雇や雇い止めをされた者(以下「被解雇者等」といいます。)は、もはや「使用者が雇用する労働者」とはいえないことから、使用者は、被解雇者等が属する労働組合の団体交渉の要求を拒否できるようにも思えます。
しかし、被解雇者等が解雇や雇い止めの有効性を争っているよう場合に、使用者が団体交渉に応じなくてよいとするのはあまりにも形式論であり、不当といえます。
 したがって、被解雇者等が解雇や雇い止めを争って、当該被解雇者等が属する労働組合が団体交渉を求めた場合、使用者は団体交渉を拒否できないと考えるべきです。
したがって、被解雇者等が解雇や雇い止めを争って、当該被解雇者等が属する労働組合が団体交渉を求めた場合、使用者は団体交渉を拒否できないと考えるべきです。
これは、被解雇者等が解雇や雇い止めの後に労働組合に加入した場合であっても異なりません。
また、学説の多くは、任意退職した労働者の属する労働組合が、退職後相当期間内に、退職金や在職期間中の残業代等を要求している場合にも、その範囲で、使用者は交渉に応ずべき地位に立つのが原則であると解しています(菅野963頁、西谷291頁)。
解雇後、長期間を経過している場合
 被解雇者が解雇後、社会通念上、合理的といえる期間内に解雇の撤回等を求めて団体交渉を申し入れている場合、使用者は団体交渉に応じなければならなりません。
被解雇者が解雇後、社会通念上、合理的といえる期間内に解雇の撤回等を求めて団体交渉を申し入れている場合、使用者は団体交渉に応じなければならなりません。
では、解雇後、正当な理由もなく、長年月が経過している場合はどうでしょうか。
このような場合は、もはや「使用者が雇用する労働者」ではなく、使用者は団体交渉を拒否できると解されています。
問題は、具体的に、どのような事情があれば、団体交渉を拒否できるかです。これを検討するために、解雇後の団体交渉が問題となった2つの裁判例を紹介します。
①【参考裁判例】三菱電機事件 東京地判昭63.12.22(労民39巻6号703頁)
この事案は、団体交渉の拒否を認めた事案です。
事案の概要
 Aは、会社Bに勤務する労働者であったが、昭和48年1月29日、転任命令を拒否したことを理由に解雇された。
Aは、会社Bに勤務する労働者であったが、昭和48年1月29日、転任命令を拒否したことを理由に解雇された。
この転任命令と解雇に関しては、当時Aの所属していた労働組合が、労働協約の定めに基づき異議申立てを行い、多数回にわたってBと協議をしたが、平行線のまま終わった。Aは、解雇に関する協議終了後間もなく、労働組合から組合員資格喪失の通知を受けた。
Aは、転任命令に関する協議不調後、その効力停止を求める仮処分を申請し、解雇後は申請の趣旨を地位保全に変更して裁判を続けるなどしていたが、解雇から7年7か月を経過した昭和55年9月1日、一般労組であるXに加入した。そして、加入後は、Xの支部や他の労働組合などで結成された支援共闘会議が中心となって、Bに対する抗議行動や交渉申入れを行っていたが、Xは、Aの解雇から8年10か月、組合加入から1年3か月が経過した昭和56年12月11日、Bに対してAの解雇撤回を交渉事項とする団体交渉を申し入れた。
これに対して、Bは、同月15日、「Aは、昭和48年1月29日付けで解雇されて社員ではなくなったこと、この解雇については当時Aが所属していた労働組合と労働協約に則り十分協議済みであり、以来9年近くを経過していること、本件に関し現に裁判所において係争中であること、したがって、団体交渉の必要はないこと」を理由として団体交渉を拒否した。
そこで、Xは、団体交渉の拒否が不当労働行為に当たるとして、労働委員会に救済命令を申し立てたところ、地労委は不当労働行為の成立を認めたが、中労委は、
「解雇された労働者がその解雇を争っている限り雇用関係が完全に消滅したことにはならず、したがって、労働組合が当該解雇について団体交渉を申し入れたときには、使用者には応諾の義務があるが、この見解が妥当するのは、労働者が解雇された後社会通念上合理的な期間内に労働組合から使用者に対して団体交渉が申し入れられた場合に限る」
とした上で、Xが申し入れた団体交渉は解雇から社会通念上合理的な期間内にされたものということはできず、その拒否は不当労働行為に当たらないとして、地労委の命令を取消し、Xの申立てを棄却した。
Xは、中労委を被告とし、棄却命令の取消しを求めて提起した。
判旨
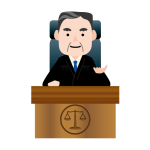 本判決は、団体交渉の拒否が不当労働行為となるのは、それが正当な理由のない場合であって、しかも、正当な理由がないことの主張、立証責任は、団体交渉拒否を不当労働行為であると主張する者にあるとの原則を明らかにした上で、
本判決は、団体交渉の拒否が不当労働行為となるのは、それが正当な理由のない場合であって、しかも、正当な理由がないことの主張、立証責任は、団体交渉拒否を不当労働行為であると主張する者にあるとの原則を明らかにした上で、
「上述した諸事情、特に、解雇当時にAが所属していた支部による支援、助力の存在、協約所定の協議が多数回にわたって行われた事実、解雇後にAがとった行動の内容、解雇から交渉申入れまでの長期間の経過、その間における特別の事情の不存在、XとBの特殊な関係、Bにとっては重複交渉となる見通しなどの事情を総合的に考慮すると、XがしたAの解雇撤回を交渉事項とする団体交渉の申入れには合理性がなく、Bが前記のような理由を挙げて拒否したことは、右事情のもとでは無理からぬものがあるということができるから、Bがした団体交渉の拒否に正当な理由がないとはいえず、したがって、右団体交渉の拒否は不当労働行為には当たらないと解するのが相当である。」
と判示した。
他方、次の裁判例は、解雇後、数年を経過しての団体交渉申入れであっても、団体交渉を拒否できないと判示しています。
②【参考裁判例】日本鋼管事件 東京高判昭57.10.7(労判406号69頁)、最判小判昭61.7.15(労判484号21頁)
判旨
 裁判所(東京高裁)は、
裁判所(東京高裁)は、
「本件の場合、解雇後Aは約6年10か月、Bは約4年5か月経過後に、団体交渉の申入れをしているが、(証拠略)を総合すれば、右両名は、昭和54年2月9日参加人全日本造船機械労働組合日本鋼管分会を結成し、同日参加人全日本造船機械労働組合に加入し、右参加人らは、同月14日控訴人に団体交渉の申入れをし、その間右両名は解雇の効力を争って裁判所に労働契約上の地位の存在することの確認請求の訴を提起していたものであって、解雇後漫然とこれを放置していたものではなく、かつ、参加人らは、組合を結成し、又は、組合は加入してから直ちに右申入れをしていることが認められる。日常の作業条件等から生ずる苦情については、これが発生したときから相当期間経過することによって、すでに解決の余地がないとか、或いは、相当でないとして、時機を失するものもあろうが、解雇に関する問題はこれと同一に解することはできず、本件の場合、右認定事実のもとにおいて、解雇から団体交渉の申入れまで長期間を経過したとしても、これをもって、団体交渉の申入れが時機に遅れたものと言うことはできない。」
とし、団体交渉を拒否した会社に対して発した救済命令が正当であると判示した。
裁判例の分析
 ①と②の事案において、結論が異なった理由として、以下の点が考えられます。
①と②の事案において、結論が異なった理由として、以下の点が考えられます。
まず、①の事案は解雇から8年10か月を経過していましたが、②の事案では、解雇から1名は6年10か月後、他の1名は4年5か月後であり、解雇後、団体交渉申入れまでの期間が①ほど長期間に及んでいませんでした。
また、①の事案は、被解雇者が解雇後、当時属していた労働組合によって団体交渉を行っていましたが、②の事案では、被解雇者らは、裁判で解雇の効力を争ってきたのみで、解雇当時所属していた組合によって団体交渉等が行われた形跡はありませんでした。
さらに、①の事案は、組合加入から1年3か月を経過してから団体交渉を申し入れたのに対し、②の事案では、団体交渉を申し入れた組合は、被解雇者らが他の従業員とともに交渉申入れの5日前に結成したものであり、被解雇者らは組合加入からは遅滞なく団体交渉を申し入れたという事情がありました。
以上から、裁判では、解雇後の団体交渉の事案において、解雇から団体交渉申入れまでの期間の長さだけではなく、その他の事情も総合考慮して、個別具体的に判断しているものと考えられます。
長期間の経過にやむを得ない事情がある場合
 雇用契約の終了後、長期間が経過した場合であっても、やむを得ない事情がある場合、使用者に団体交渉に応じる義務(団体交渉応諾義務)が課される場合があります。
雇用契約の終了後、長期間が経過した場合であっても、やむを得ない事情がある場合、使用者に団体交渉に応じる義務(団体交渉応諾義務)が課される場合があります。
例えば、アスベスト被害など長期の潜伏期間の後に初めて症状が発生するような疾患に関して、労働者が退職後、労働組合を通じて補償を求める場合などです。
住友ゴム工業事件(大阪高判平21.12.22労判994号81頁)において、裁判所は、在職中、石綿作業に従事して退職後6年から16年が経過した元従業員が加入する組合からの石綿被害補償に関する団体交渉申入れについて、以下のとおり、団体交渉応諾義務の要件を示しました。
「団体交渉を通じ、労働条件等を調整して正常な労使関係の樹立を期するという上記労組法の趣旨からすれば、使用者が、かつて存続した雇用関係から生じた労働条件を巡る紛争として、当該紛争を適正に処理することが可能であり、かつ、そのことが社会的にも期待される場合には、元従業員を「使用者が雇用する労働者」と認め、使用者に団体交渉応諾義務を負わせるのが相当であるといえる。その要件としては、①当該紛争が雇用関係と密接に関連して発生したこと、②使用者において、当該紛争を処理することが可能かつ適当であること、③団体交渉の申入れが、雇用関係終了後、社会通念上合理的といえる期間内にされたことを挙げることができる。そして、上記合理的期間は、雇用期間中の労働条件を巡る通常の紛争の場合は、雇用期間終了後の近接した期間といえる場合が多いであろうが、紛争の形態は様々であり、結局は、個別事案に即して判断するほかはない。」
 その上で、裁判所は、
その上で、裁判所は、
「本件の団体交渉申入れが合理的期間内にされたといえるかを検討するに、上記認定の事実経緯によれば、石綿関連疾患は非常に長い潜伏期間があり、長期間経過した後に症状が発生するものであること、Fは平成17年7月にC及びDを代理人として、参加人に対し、Eの職場歴と胸膜悪性中皮腫との関係を調査してくれるよう依頼したこと、当初、参加人は、Eの悪性中皮腫と業務との関係は不明であると主張していたこと、厚生労働省が平成18年に作成した手引きにおいては、C及びDが従事していた業務で使用したタルクに不純物として石綿が混入している場合があると指摘されていること、同年10月6日にC、D及びFが被控訴人に加入して分会を結成し、参加人に対し、団体交渉を求めたことなどの事情が認められる。このような事情からすれば、C及びDが参加人を退職してから相当の期間が経過しているものの、その責をCらに帰することは酷であり、石綿被害の特殊性を考慮すれば、社会通念上、合理的期間内に団体交渉の申入れがされたと解するのが相当である。」
と判示しました。
これは、発症まで極めて長期間かかるというアスベスト被害の特殊性を考慮した例外的な事案といえます。
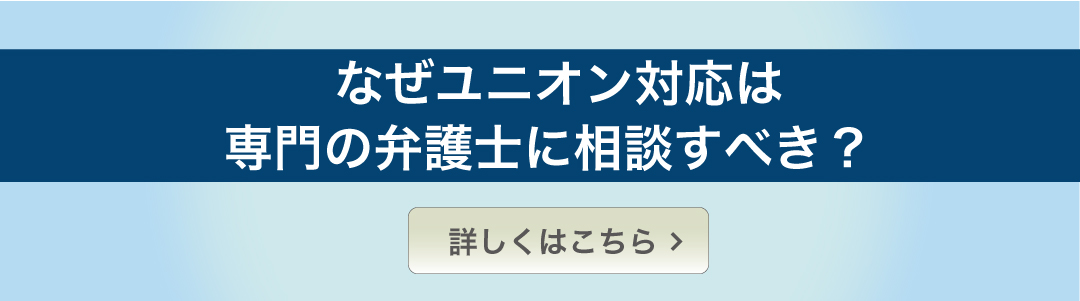
その他の関連Q&A
-
1
ユニオン・合同労組とは? -
2
不当労働行為とは? -
3
労働委員会の手続等 -
4
組合活動の妥当性 -
5
団体交渉への対応方法 -
6
労働協約とは? -
7
争議行為への対応 -
8
紛争の解決制度